
マンションの選び方のポイントが分かりません。
どんなところを見れば良いマンションを選べますか?
こんな疑問に答えます。
マンションを買おうと考え始めたけれど、どうやって選べば良いかわからない・・・
チラシを見るとどれも良さそうに見えるけど、良いマンションを見極めるポイントはどこなの?
あなたもそんな風にお感じかもしれません。
確かに新築でも中古でもそのマンションが本当に優良な物件なのかなかなか判断しにくいですよね。
全てが完璧な物件というのはなかなか無いのですが、いくつかの大切なポイントをチェックしていけば、少なくともそのマンションが買うべき物件なのかどうかが見極められるようになります。
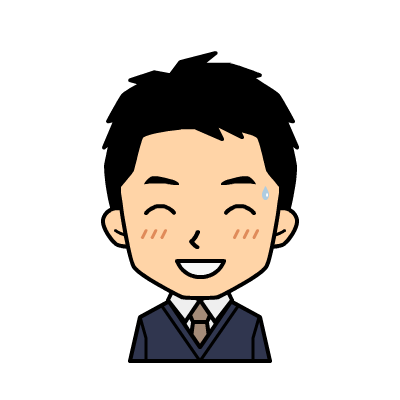
この記事では、客観的にそのマンションをチェックするためのいくつかのポイントを紹介してきますので、是非参考にしていただければ嬉しいです。
この記事を読むと分かる事
- マンションを買う前に考えるべき6つのポイントが分かります
- いろいろな種類のマンションのメリットとデメリットが分かります
- 自分がどんなマンションを選ぶべきかが分かるようになります
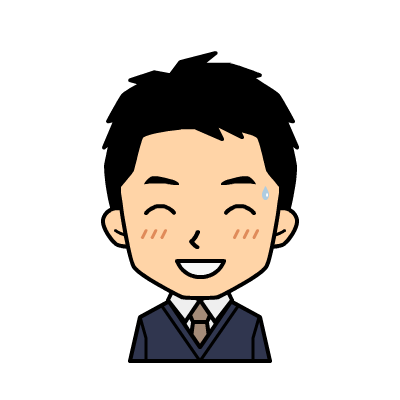
この記事を書いている私モトキは、不動産会社を経営者兼店舗の責任者として10年ほど運営してきました。このメディアでは、その知識と経験に基づいた暮らしと不動産に役立つ有益な情報を発信しています。
マンションを買う前に考えるべき6つのポイントとは?

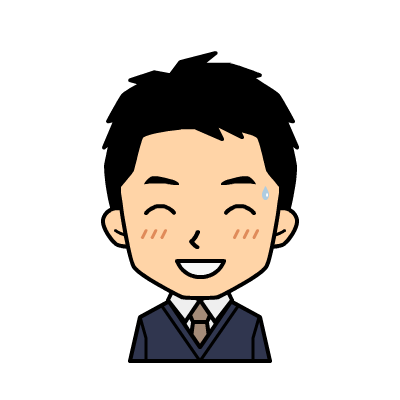
ここから、マンションを買う前に考えるべきポイントを6つ解説していきます。
マンションを買う事を考え始めたというあなたにも参考となる情報ですので是非最後までお付き合いください。
6つのポイント
- 新築も中古も検討する事
- 立地はどうか?
- 管理状態はどうか?
- 適切な世帯数か?
- 維持費は適正か?
- 防音性能は十分か?
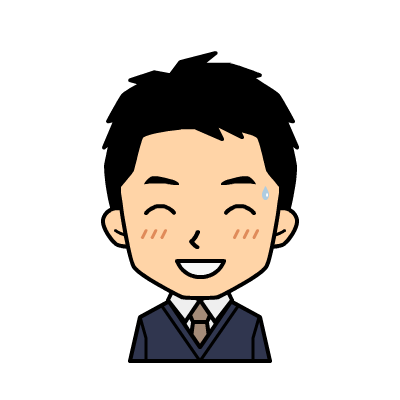
1.新築も中古も検討する事

マンションを買う事を検討しているのであれば、予算内の新築マンション、中古マンションの両方検討する事をおすすめします。
新築だけ、中古だけという様に選択肢を最初から狭めないで、本当に良いマンションであれば候補に入れてみるようにしましょう。
良いマンションであるかどうかは、新築か中古かという事よりも、立地や管理といった事の方が重要です。どんなポイントを見るべきか、詳しくは次の項目から紹介していきます。
もちろん、新築・中古それぞれにメリット・デメリットがありますし、どちらが好きか、という好みの問題もあると思います。それぞれのメリット・デメリットを再度確認しておきましょう。
中古マンションのメリット
- 価格が新築に比べて安い
- 管理状態を確認できる
- 隣人などの住人を事前に知れる
中古マンションのデメリット
- 設備など古くなっている
- リフォームが必要になる
- 住宅ローン減税を受けるためには条件がある※
※住宅ローン減税を受けるためには、築25年以内、または新耐震基準に適合する建物である事が必要
新築マンションのメリット
- 最新の設備
- 全てが新品である事
新築マンションのデメリット
- 管理状態や隣人の事などは事前にわからない
- 新築プレミアムが価格に乗っている
新築プレミアムって?
一度人が住めばそのマンションは中古になります。その時点でどんなマンションでも少なからず価格が下がります。下がった金額が新築プレミアムという事です。
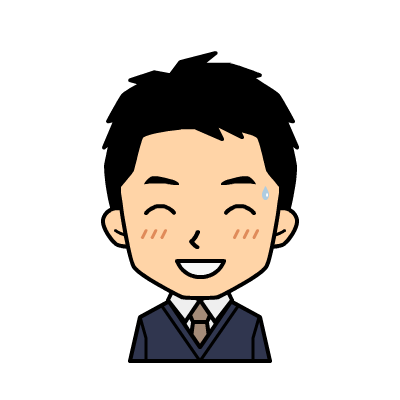
どうしても全てが新品でなければだめ!という人には新築マンションをおすすめしますが、中古でもリフォームをすれば新築のような内装にする事ができますし、その他の条件を満たすマンションであれば、検討してみる事をおすすめします。
2.立地はどうか?

マンションを買う時に、立地は最重要項目の一つです。マンションに住む人は基本的に便利な生活を求めています。好立地のマンションは将来的にも値下がりもしにくく、資産価値も高いと言えます。
とはいえ、好立地のマンションは、生活環境としては良くない場合もあります。道路や鉄道、繁華街からの騒音や光害などの問題もあります。治安の問題もあるかもしれません。特に子供がいる家庭の場合は、学校への通学ルートが安全かどうかも重要です。
逆に、静かな郊外のマンションの場合、住環境は良くなりますが、駅までの通勤は少し不便になるかもしれません。また、立地の悪いマンションは将来的に売却しようとする場合、買手が見つかりにくく、価格が下がってしまう可能性もあります。
ココがポイント
利便性と生活環境のバランスの良い立地を選ぶのが理想です。
3.管理状態はどうか?

立地と同じように重要なのは、マンションの管理状態です。
中古マンションの場合には、すでに管理組合があり、管理会社も決まっているので、物件の共用部分を良く観察したり、管理会社が発行する「重要事項に関わる調査報告書」を確認する事によって状態を判断します。
共用部分が汚れていたり、ゴミが放置されていたりするようなマンションは管理の状態が良くありません。マンション全体で管理費や修繕積立金の滞納が多いという様な場合は、将来的に問題が起きる可能性が高いです。
新築マンションの場合は、将来的にもきちんとした管理が続けられる体制がきちんと整っているかどうかをチェックしましょう。
安い管理費用が設定されている場合もありますが、きちんとした管理会社に適正な管理費用を支払わなければ、適正な管理は期待できません。
また、安すぎる修繕積立金も将来的には資金不足に陥りメンテナンスができなくなる可能性が高いですし、大幅な値上げをする必要が出てくるので将来の所有者に大きな負担がかかる事になります。つまり、将来売却する時に障害になる可能性があるという事です。
4.適切な世帯数か?

マンションの規模と世帯数は、管理や住環境にも影響を与えるので重要です。
小規模でも大規模でもそれぞれメリット・デメリットがあるので、良く理解した上でちょうど良い規模の世帯数のマンションを選ぶようにしましょう。
さらに詳しく
大規模マンションとは世帯数が100戸以上、小規模マンションとは世帯数が50戸以下のマンションの事を言います。
小規模マンションのメリット
- 防犯意識が高くなる
- 意思決定がしやすい
防犯意識が高くなる
プライバシーが少ない事の裏返しですが、小規模マンションの場合は、住民同士が顔見知りになりやすく、関係性が近くなるので空き巣や不審者の侵入を防ぎやすくなり、防犯上はメリットとなります。
意思決定がしやすい
大規模修繕や建て替えなど、大きな意思決定をする際にも、大規模マンションと比べれば、お互いに協力しようという空気が生まれやすく結果意見をまとめやすくなります。
小規模マンションのデメリット
- 管理費修繕費が高くなりがち
- プライバシーが少ない
- 環境が変わる可能性がある
管理費・修繕費が高くなりがち
小規模なマンションの場合、少ない世帯で建物全体の維持管理する費用を捻出していかなければなりません。あまりにも小規模なマンションは、将来的に管理費、修繕積立金が高くなっていく可能性が高いです。
プライバシーが少ない
小規模のマンションの場合、住民同士の関係性がどうしても近くなるので、プライバシーが守られにくいと感じる人もいる事でしょう。
環境が変わる可能性がある
小規模のマンションの場合、敷地がどうしても狭くなるので、周辺の土地に別の大きな建物が立つと眺望や日当たりが変わってしまう事があります。
大規模マンションのメリット
- 共用施設が充実している
- 管理費・修繕費が安い
- 景観が変わりにくい
共用施設が充実している
大規模マンションの場合、世帯数が多いので充実した共用施設を維持する事ができます。敷地内にコンビニや公園、ジムやプールといった施設があるマンションもあります。
管理費・修繕費が安い
大規模マンションは戸数が多いため、1戸あたりの負担額を安くする事ができます。
景観が変わりにくい
敷地が広いため、周辺に他の建物が建ってもあまり眺望や日当たりに影響を与える事がありません。
大規模マンションのデメリット
- エレベーターが混む
- 防犯面でやや難がある
- 意思決定がしにくい
エレベーターが混む
大規模マンションの場合、通勤、通学の時間帯にエレベーターが混み、乗れるまで時間がかかる事があります。
また敷地が広いため、駐車場や駅やバス停に行くまで意外に時間がかかるという事もあります。
防犯面でやや難がある
大規模なマンションの場合、敷地内に誰でも入れる部分が多くなります。また、住民同士があまり顔を知らないため、関係のない人が建物の中に入ってきても分かりづらいという事もあります。
意思決定がしにくい
大規模マンションの場合、住民に仲間意識が生まれにくく、また戸数が多ければそれだけ様々な種類の住民が住む事になるため、何かの意思決定が必要な時に意見がまとまりづらくなります。
ココがポイント
大規模マンション・小規模マンションのそれぞれのメリット・デメリットを踏まえた上で、適正な規模のマンションを選ぶ様にしましょう。
5.維持費は適正か?

マンションを買う上で、維持費をきちんと把握しておく事は非常に大切です。管理費・修繕費は、マンションを所有している間、払い続ける必要があります。維持費を長期にわたって負担していく事が可能かどうかは、マンションを買う上で確認するべき重要な項目です。
新築時は管理費も修繕費も安く設定されている事が多いですが、将来的には必ずと言って良いほど値上がりします。中古マンションを買う場合も、管理費、修繕費が値上がりする計画が無いかどうかを事前に確認しておくべきです。
ココに注意
小規模マンションのデメリットのところで書きましたが、戸数の少ないマンションは、築年数が経っていくにつれ必要になってくる大規模修繕工事の費用を少ない世帯でまかなう必要があるため、1戸あたりの負担額がどうしても大きくなりがちです。
また、世帯数の多い大規模なマンションでも、共用の施設が多すぎると、将来、管理費や修繕費の高騰を招く危険があります。便利で魅力的な施設も将来的には大きな費用の負担となる可能性がある事を覚えておきましょう。
駐車場の数が多い場合も、将来車を持たない世帯が増えてきた場合に、空いた駐車場の分の収入が管理組合に入らなくなり収支の計画が崩れてしまい各世帯の負担増につながる可能性があります。
6.防音性能は十分か?
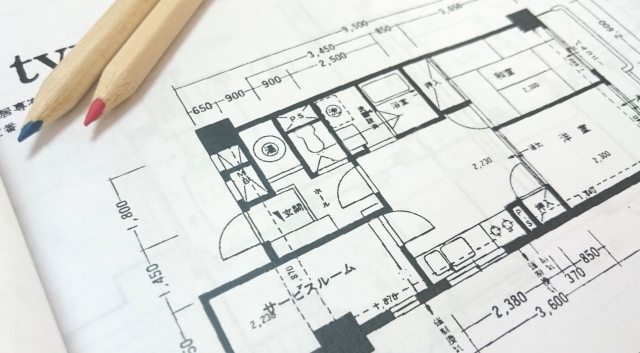
マンションを買った後に起こるトラブルの多くが騒音の問題です。
どんなマンションでも、複数の人が同じ建物の中で暮らしていく以上、騒音の問題をゼロにする事は不可能です。とはいえ、防音性能が高ければ、快適に過ごす事ができ、トラブルが起こる可能性も減らす事もできます。
防音性能確認のポイント
- 遮音性能
- 床のコンクリートスラブの厚さ
- 壁の厚さ
- 水回り配管の位置
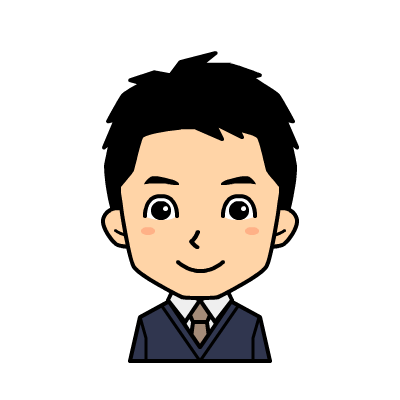
上記のポイントを一つずつ解説していきます。
遮音性能を確認する
マンションなどの遮音性能は数値で表す事ができます。騒音には二種類あり、物を落としたり椅子を引きずったりする「軽量床衝撃音」と、人が歩いたり飛び跳ねたりする時に起きる「重量床衝撃音」です。
軽量床衝撃音に対しては「LL-45」、重量床衝撃音に対しては「LH-50」というような数値で遮音等級を表し、数値が小さいほど遮音等級が高いという事になります。
床のスラブ厚は20cmから30cmは必要
軽量床衝撃音に関しては、遮音等級の高い床材を使う事で軽減します。ほとんどのマンションで「LL45等級」以上の遮音性能を持つ床材が使われているはずです。
重量床衝撃音に関しては、床のコンクリートの厚みが影響します。遮音性能を考えるとコンクリートスラブの厚さは20cmから30cmほど必要でしょう。
ココに注意
最近のマンションはスラブ厚20cm以上が一般的ですが、中古のマンションではもっと薄いものもあるので注意が必要です。
隣家との壁厚は18cm以上が目安
マンションの騒音の問題は、上下階だけではありません。隣の家からの騒音についても確認する必要があります。隣の家からの騒音は、壁の厚さと構造によって変わり、隣の家と自分の家を隔てているコンクリート壁の厚さは、18cm以上が目安です。
隣の家への騒音は空気を伝っていく音が原因で、その遮音性能は「D-50」、「D-55」という様にD値で表され数字が大きくなるほど遮音性能が高いという事になります。
壁の構造も遮音に影響しますので確認が必要です。構造スリットや二重壁は遮音性能を下げる可能性があります。
ごくまれに壁に構造スリットという隙間を設けているマンションがあり、コンクリート壁にこの様な隙間があると、壁に厚さがあったとしても、その部分から音が伝わりやすくなってしまいます。
壁が二重壁の場合、特にGL工法の壁など、コンクリート壁にボンドなどでプラスターボードを貼って仕上げた壁は遮音性能が低下する可能性があります。理由としては、空洞の部分に音が太鼓の様に(太鼓現象という)共鳴してしまうからです。
さらに詳しく
最近の分譲マンションでは、GL工法ではなく、コンクリート壁に接しない下地を組んだ上に、プラスターボードを貼りクロスで仕上げる場合が多くなっています。
水回り、配管が寝室に接していないか
特に騒音を感じるのは、夜寝室で寝ている時では無いでしょうか?夜の騒音で意外と気になるのが、他の部屋の排水が流れる音です。
水回りの配管の位置も忘れずにチェックしておき出来るだけ音が響かない様に設計されているマンションを選ぶ様にしましょう。
マンションの場合、排水管が上下に通っているのでどうしても音がしてしまうのですが、配管が通っているスペースが寝室と接していると、排水音がさらに部屋に響きやすくなってしまいます。パイプスペースと部屋との間にクローゼットなどが設置されていたりすると騒音が軽減されます。
さらに詳しく
図面上で「PS」と書かれている部分は「パイプスペース」の事で、トイレの近くにあってその中に排水菅が縦に通っている事が多いです。
ココがポイント
騒音の問題は、マンションを買った後によく生じるトラブルの一つです。マンションを選ぶ時には防音性能にも気を配る様にしましょう。
まとめ

新築でも中古でもマンションにはたくさんの種類があります。選ぶ時には、規模や立地、管理など、確認するべきポイントがたくさんあります。
実際、家探しにおいて全てを完璧に満たす物件を見つけるのはほぼ不可能です。
どのポイントを重視するのか、どのポイントは絶対に外せないのかという希望条件の順位付けをしつつマンションを選ぶようにしましょう。
上位の希望条件を満たすマンションであれば、買っても後悔する事は無いと思いますよ。
この記事の内容が、少しでもあなたのマンション選びの参考になれば嬉しいです。

